
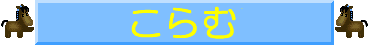 本との出会い
本との出会い
ホームページをリニューアルして、新しく「コラム」というコンテンツを設けました。
ホームページでよく「日記」を書かれている方がいますが、私はそんなにマメではないので、
「コラム」というタイトルにしました。ここには私が思ったこと,感じたことをとりとめなく
綴っていこうと思います。
と言っても、そんなにたくさんのコラムを書く自信もなく、かといってコンテンツの中身が
何もないということではまずいので、とりあえず今回は「本との出会い」について書こうと思います。
私は昔から数学や理科が大好きで、高校で理科系・文化系の選択をする際も迷わず理系を選びました。
手元に5歳頃自分が書いたメモが残っています。ここには数字と訳の分からない線が無数に書かれています。
当時、医者が書くカルテというものに興味があったので、訳の分からない線は、
医者が書いたドイツ語の筆記体を真似ているものと思われます。
医学用語のつもりで書いたものと数字だけが存在するメモ。そんなものを5歳頃に書いている自分って、
典型的な理科系人間だな、と思ってしまいます(ただ、話し方は文化系っぽいとよく言われますが)。
逆に、昔から国語は大っ嫌いで、「読書」なんていう言葉は、自分の頭の辞書には含まれていませんでした。
小学校の読書感想文の宿題も、飽きっぽい性格から最初の20ページくらいで本を読むのをやめてしまい。
「あとがき」を写して何とかごまかすことしかした覚えがありません。
そんな読書嫌いな私に、ある方が本を紹介して下さいました。星新一著「ようこそ地球さん」(新潮文庫)です。
星新一さんは残念ながら1997年12月に他界されましたが、SF小説の第1人者の1人です。
星さんの特徴は、何と言っても文庫本で20ページにも満たないお話をいくつもお書きになるという点です。
俗に、ショートショートと呼ばれているものですが。
したがって、20ページで飽きてしまう私でも、1話は必ず読めるというわけです。
私も読書の楽しみがだんだんとわかるようになり、星さんの文庫本を買いあさりました。
私の読書の原点は、星新一さんです。
読書嫌いな方は、星さんのショートショートから慣れ親しむことをおすすめします。
ショートショートで「本」と付き合えるようになり、次第に長編小説にチャレンジしたいと思うようになりました。
そこで偶然本屋で手にとったのが、松本清張著「点と線」(新潮文庫)でした。
松本清張さんはご存じ推理小説作家で、探偵(警察)と犯人のやりとりが巧妙に描かれています。
漫画でいうと「名探偵コナン」が近いでしょうか(私は一切漫画は読まないので、よくわかりませんが)。
ただ、漫画やテレビとは違い、活字でその場面を読むということは、読者の想像力を駆り立て、
読者が主人公になった錯覚さえ覚えることがあります。
私もたまたま本屋で手にとっただけなのに、その場で夢中で読んでしまい、
気づいたら、本の3分の1ほど読んでしまっていました。
もちろん続きが気になるので、その本を買いましたが、結局2日で全部読んでしまいました。
小説の良いところは、自分が主人公になれること。
松本清張さんの推理小説では、まさに自分は探偵になれます。
ここまで来られれば、だいたいの小説は普通に読めるようになりました。
少し教養のために、と思い、三島由紀夫著「金閣寺」(新潮文庫)を買いました。
また、ちょうどこの頃、大江健三郎さんがノーベル文学賞を受賞されたということもあって、
大江健三郎著「個人的な体験」(新潮文庫)も買って読みました。
ただ驚いたのは、この2つの作品は、いずれも少しだけですが女性との官能シーンが描かれているんですよね。
人間の欲にはいろいろなものがありますが、性欲についても巧みに表現されており、
このあたりが一流の作家なのかなぁ、と思ったりもします。
これまで、いろいろな小説を読んできましたが、最近はまっているのが椎名誠さんです。
最初に読んだのが「新橋烏森口青春篇」でした。
これはいわゆる「私小説」というジャンルのもので、椎名さんがサラリーマンだった時代のことを小説風に書いてあります。
そこには、中小企業のはちゃめちゃさや、青春時代の淡い恋の話がおもしろおかしく描写されており、
主人公と現在の私が同じような年代,立場であることで共感が持てたのかもしれません。その後、
- 入社前の木村晋介,沢野ひとしらと共同生活していた頃の話が書かれている椎名誠著「哀愁の町に霧が降るのだ(上・下)」(新潮文庫)
- サラリーマン時代のことがさらに詳しく書かれている椎名誠著「銀座のカラス(上・下)」(新潮文庫)
- 「本の雑誌」創刊からサラリーマン時代終焉までが書かれている椎名誠著「本の雑誌血風録」(新潮文庫)
- 「本の雑誌」とともに「作家」として歩み出した様子が書かれている椎名誠著「新宿熱風どかどか団」(朝日文庫)
と、椎名誠私小説シリーズ7冊を読破してしまいました。
つまり、椎名さんの青春時代から作家として歩み出すまでのおよそ20年間の歴史を読んだことになります。
私は、独り言をつらつらと綴ったような文調が大好きで、私もふと気になっていることが椎名さんも気になっているなんて書いてあると、
すごく共感してしまいます。要するに、普段人には言わないようなとりとめのないことも書いてあったりするんですよね。
あと、椎名さんの小説で好きなのは、忘れた頃に淡い恋の話がポツポツと出てくるところですね。
青春時代の私小説とはいっても、恋愛のことばかり書いてあるわけではなく、むしろ男臭い生活が描かれていて、
かといって、恋愛のことがまったく触れられていないわけではなく、恋愛になるとぎこちなくなる椎名青年がいたり、
時には若い頃には誰もが犯すであろう失敗もしたりと、本当にありがちなことが描かれているので、妙に共感を覚えてしまいます。
ただ、「新橋烏森口青春篇」と「銀座のカラス」の同じ場面で出てくる女性が微妙に異なっていたり、
「銀座のカラス」と「本の雑誌血風録」の間で結婚されているはずなのに、その話は全く出てこなかったり、
といった点があり、椎名さんも恋愛の話を書くときはこっ恥ずかしくなるものなのかなぁ、と想像してしまいます。
その他の椎名シリーズでは、
- 記念すべき処女作、椎名誠著「さらば国分寺書店のオババ」(新潮文庫)
- 「本の雑誌」を一緒に立ち上げた目黒孝二著「本の雑誌風雲録」(角川文庫)
- 「本の雑誌社」で5年間働いた群ようこ著「別人・群ようこができるまで」(文春文庫)
を読みました。「本の雑誌」創刊時の話は、3人の方がそれぞれの視点で書かれているので、
自分があるときは椎名誠、あるときは目黒孝二、あるときは群ようこになって読むことができ、とても面白かったです。
3人が同じ場面を違う視点で書いているものなんてなかなかないと思います。
私はご存じの通り競馬好きで、競馬ものでは「週間Gallop」の藤代三郎著「馬券の真実」という連載が好きなのですが、
藤代三郎さんって実は目黒孝二さんのペンネームなんですよね。今まで全く知らなかったのですが、
自分の好きな作家どうしが、実は友達だったことを知って、ちょっと笑ってしまいました。
私は、読みたい本は必ず買うようにしています。一度読んだ本って、しばらくするとまた読み返したくなっちゃうんですよね。
また、本棚に本がきれいに並んでいると、自分の宝物って感じがするので好きです。
これからも、本は自分の財産にしていきたいと思っています。